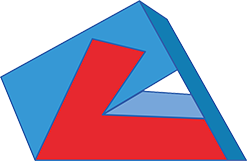日本のロックシーンにおいて――いや、「ロックシーン」なんて窮屈な枠は取り払ってしまおう――日本の音楽界において、一つの世代(現在30代前半)を代表する突出した才能を持つ2人のソングライター、小山田壮平と長澤知之が組んだバンド。それがALだ。21世紀の日本に突然現れたレノン&マッカートニー? というより、資質的にはレノン&レノンと言った方がいいだろうか。小山田壮平はandymoriのメンバーとして、長澤知之はソロアーティストとして、これまで数々の名曲を残してきた。そんな2人が、どうしてこのタイミングでバンドを組んだのか?
同郷(福岡)にして同学年(1984年生まれ)にしてデビューもほぼ同時期の二人は、これまでずっと同じ時代の空気を吸いながら同じ景色を見てきただけでなく、実はデビュー前から「お互いに一目を置く」ミュージシャン同士として深い交流を持っていた。そして、これは一部のファンにしか知られていなかったことだが、長澤知之がソロアーティストとして旺盛な音楽活動をしていて、andymoriにまだ解散の予兆などまったくなかった時期から(最初のライブは2011年)、2人は断続的に小さなライブハウスのステージに立って、そこでALとして新曲を演奏していた。それぞれ別の事務所、レコードレーベルに所属する「大人」として当時はこっそりとやるしかなかったわけだが、それでも、どうしてもやらずにはいられない「熱」がその時点でもう生まれてしまっていたのだ。
2014年10月の武道館公演をもってandymoriが解散した後、小山田壮平は「ALを本気でやりたい」という強い想いを伝えるために長澤知之に手紙をしたためた。そして、2人だけの理想郷だったALは、本格的に始動をする上でバンドとしての活動に踏み出した。何よりも、彼らが一緒に書いてきた楽曲が「バンドで音を鳴らすこと」を求めていたからだ。そこで2人が心を通わせることができ、その楽曲をさらに遠くまで飛ばすことができる特別なプレイヤーとして、そこに藤原寛と後藤大樹が加わることとなった。それが、AL誕生のストーリーだ。
「ソロでやるってことはまったく考えてなかった。andymoriを解散するって決めた瞬間から、ALのことしか頭になかった。自分が生きていて、これからこの世界に何を残せるかって考えた時に、自分にとって最大限のことができる場所がALだと思った」(小山田壮平)
「自分には、素敵なバンドの中でいつも一生懸命ベースを弾いていたいって気持ちしかない。だから、ALに誘われてそれを断る理由は何もなかった。(長澤)知之の曲は昔から聴いていて、『一緒にやったらどんなことになるんだろう?』って想像していたから」(藤原寛)
「andymoriを途中で脱退した後も、ずっとバンドをやりたいと思ってた。必死になって目の前のドラムを叩いていただけの昔と比べて、今はもっと“バンドをやっている”という実感がある。3人じゃなくて、4人っていうバランスがいいのかもしれない」(後藤大樹)
「例えば(小山田)壮平が野原を駆け回るような詞を書いて、僕は部屋に籠って窓から外を眺めているような詞を書く。そこで美しいと思うものは違っていても、お互いが美しいと思うものを想像できる。それを音楽にしていくのはとても楽しい」(長澤知之)
ALのファーストアルバム『心の中の色紙』で最も不思議で、最も感動的なのは、曲によって、これまでのどんな曲よりも小山田壮平のパーソナルな部分や、長澤知之のパーソナルな部分が露になっていることだ。2人のソングライターがお互いの共通点を見出して一緒に曲を作るのではなく、お互いの違いを理解し合い、その相手からの理解を命綱にして、それぞれがより深い場所にまで潜っていくことができる。そんな「秘密の場所」でリズムを鳴らすことができるのは、昔から2人と近い場所にいた藤原寛と後藤大樹でなくてはならなかった。
30代前半という年齢的にも、ここに至るまでの作品の充実度的にも、それぞれキャリアのピークにあった2人のソングライターが、旧知の仲間たちと一緒にまったく新しいバンド活動を継続的に行う。そんな、日本の音楽界において過去にほとんど前例が思い浮かばないバンドであるALは、ファーストアルバム『心の中の色紙』で早くもその底知れないポテンシャルを全開に放ってみせた。
宇野維正(音楽ジャーナリスト)